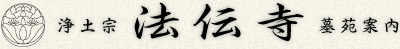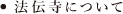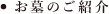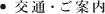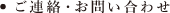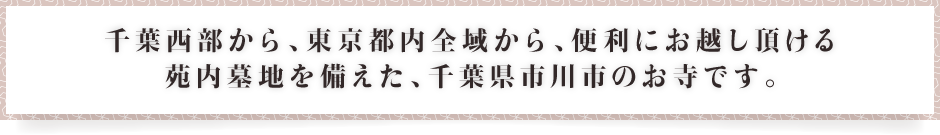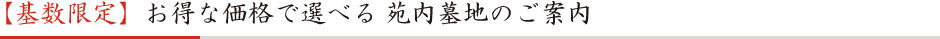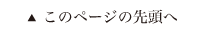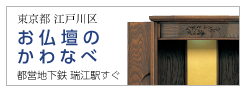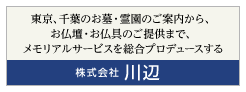法伝寺墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内
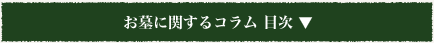
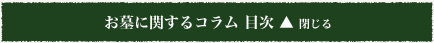
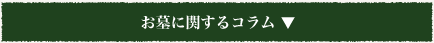
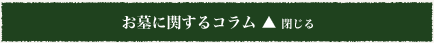
一人っ子同士の結婚。両家墓を建てたい
両家墓とは、2つの家を1つに祀ったお墓です。長男・長女同士の結婚や、一人娘の結婚などでお墓を承継される方の負担が増えたり、承継される方がいらっしゃらない場合が増えたことによって選ばれるようになりました。
以前は1つの墓石に両家の家名を記すことが多かったのですが、現在は墓石には「愛」「やすらぎ」などの言葉を彫刻し、香炉や花立て等に家紋や家名を記すことが増えているようです。
また、広い墓所に両家のお墓を並べることも両家墓のひとつの形態です。
浄土宗の年中行事(3)
4月7日
宗祖降誕会
法然上人が現在の岡山県で長承2(1133)年に生まれたことを喜び、その遺徳をしのぶものです。この日、浄土宗の各寺院では香華を供え、誕生に際しては天から上人が降りて来たという故事に因んで白旗が2本立てられます。
7月6日
記主忌
弘安10(1287)年に89歳で往生した浄土宗の第3祖、然阿良忠上人の命日の法要です。上人は、その送り名が「記主禅師」とされたことからもわかる通り、数多くの著述を行い、浄土宗の教学を大成させました。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
浄土宗 法伝寺 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Hodenji Boen Annai .All Rights Reserved.